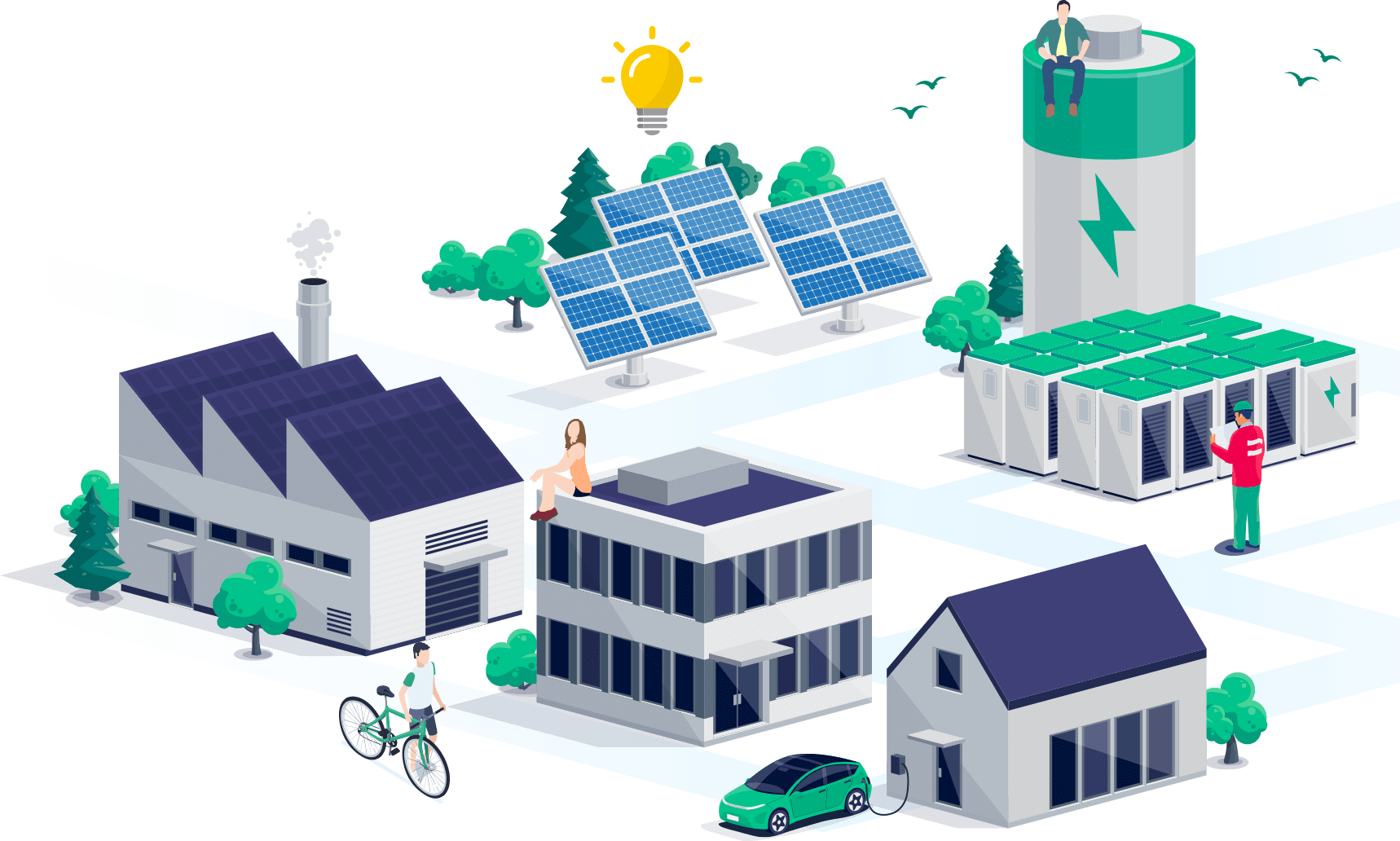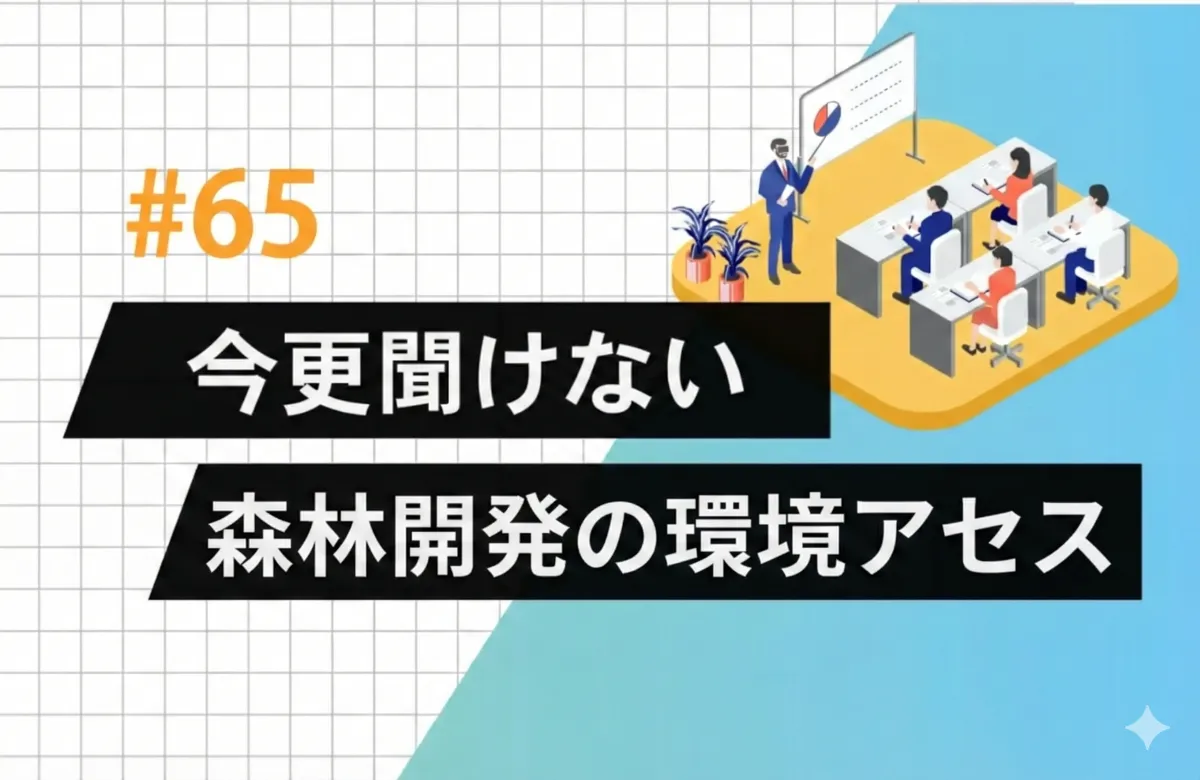今更聞けない森林開発の環境アセス
小規模でも必須な自然保護の境界線
再生可能エネルギー事業、特にメガソーラーや風力発電所の建設において、最大のハードルとなるのが「場所」の選定とそれに伴う法規制です。中でも森林を切り開く際に避けて通れないのが「環境アセスメント(環境影響評価)」です。多くの事業者が「大規模な開発でなければ関係ない」と考えがちですが、実は100ヘクタール未満の事業であっても、条例や独自規制により厳格なアセスメントが求められるケースが急増しています。
本記事では、再エネ開発と自然保護の境界線となる環境アセスの基礎知識から、アセス逃れと誤解されないためのコンプライアンス実務までを詳しく解説します。
環境アセスメント法の基礎と再エネ事業における適用基準
環境アセスメントとは、大規模な開発事業を行う際、事前にその事業が環境に与える影響を調査・予測・評価し、その結果を公表して住民や行政からの意見を聴く手続きのことです。これは単なる「調査」ではなく、事業計画そのものを環境配慮型へと練り上げるためのプロセスと位置づけられています。まずは、国の法律である「環境影響評価法(法アセス)」が定める基準を整理しましょう。
第一種事業と第二種事業の違いおよびスクリーニング制度
法アセスでは、対象となる事業を規模に応じて「第一種事業」と「第二種事業」に分類しています。第一種事業は、環境への影響が著しいと想定される大規模なもので、必ずアセスメント手続きを行わなければなりません。一方、第二種事業は第一種に準ずる規模のもので、個別に環境影響の程度を判定し、アセスメントが必要かどうかを決める「スクリーニング」という手続きを経る必要があります。この判定は、事業の内容だけでなく、地域の自然的社会的条件も考慮されるため、規模が基準値ギリギリの場合は特に注意が必要です。
太陽光発電所建設における法的な規模要件の変遷
太陽光発電事業は当初、法アセスの対象外でしたが、急速な普及に伴う森林伐採や土砂災害のリスク増加を受け、2020年4月から対象に追加されました。現在の基準では、出力40メガワット(MW)以上の太陽光発電事業は「第一種事業」、30メガワット以上40メガワット未満は「第二種事業」と定められています。面積要件ではなく出力要件が基本となっていますが、パネル設置面積が広大になるメガソーラーの場合、必然的に数十ヘクタール規模の森林開発を伴うことになります。風力発電についてはさらに厳しく、出力10メガワット以上が第一種事業となります。
100ヘクタール未満でも要注意な自治体条例と独自規制
「うちは出力30メガワット未満だからアセスは不要だ」と判断するのは時期尚早です。国の法律とは別に、各都道府県や政令指定都市が独自に定めている「環境影響評価条例(条例アセス)」が存在するからです。再エネ開発の現場では、法アセスよりも、この条例アセスの基準に抵触するかどうかが大きな争点となります。
都道府県および市町村条例による上乗せ規制の実態
多くの自治体では、地域の自然環境を守るために、法アセスよりも厳しい基準を設けています。例えば、ある県では「敷地面積が20ヘクタール以上の開発」を対象としていたり、別の県では「森林の伐採面積が10ヘクタール以上」でアセス手続きを義務付けていたりと、基準は千差万別です。さらに、重要里地里山や水源地域など特定の保護エリアにかかる場合は、わずか数ヘクタールの開発であっても簡易アセスや事前協議を求める条例を持つ自治体もあります。100ヘクタールどころか、10ヘクタール単位の計画であっても、必ず候補地の自治体条例を確認しなければなりません。
林地開発許可制度との関連性と重複する手続き
森林法に基づく「林地開発許可制度」も忘れてはなりません。1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える民有林を開発する場合、都道府県知事の許可が必要です。この林地開発許可の審査基準には、災害の防止、水害の防止、水の確保、環境の保全という4つの要件があり、実質的に環境アセスメントに近いレベルの調査と対策が求められます。条例アセスの対象外であっても、林地開発許可の申請において、動植物調査や景観シミュレーションなどの資料提出を求められるケースが一般的であり、工期やコストへの影響は甚大です。
環境アセスメントの具体的なプロセスと期間の目安
環境アセスメントは、一朝一夕に終わるものではありません。法アセスの場合、手続き完了までに通常3年から4年、条例アセスでも1年から2年程度の期間を要します。事業スケジュールを組む上で、この期間を見落とすと致命的な遅延につながります。
配慮書・方法書・準備書・評価書の4段階フロー
アセスメントの手続きは、大きく分けて4つの段階を踏みます。
1. **配慮書**:事業の早期段階で、複数案の比較など環境保全への配慮事項をまとめる。
2. **方法書**:どのような項目を、どのような方法で調査・予測するかを決め、住民等の意見を聞く。
3. **準備書**:実際に調査・予測・評価を行った結果案を公表し、環境大臣や知事、住民の意見を聴取する。
4. **評価書**:寄せられた意見を踏まえて準備書を修正し、最終的な評価結果として確定させる。
この各段階において、公告・縦覧期間や意見書の提出期間が法的に定められており、手続きを省略することはできません。
住民説明会と公聴会における合意形成のポイント
アセスメント手続きの中で最も難航しやすいのが、住民とのコミュニケーションです。方法書や準備書の段階で開催される説明会では、単に計画を説明するだけでなく、地域住民の不安や懸念に真摯に向き合う姿勢が問われます。「景観が悪化する」「土砂崩れが心配だ」「希少な鳥がいなくなる」といった意見に対し、科学的な根拠に基づいた回答と、具体的な低減措置(緩衝緑地の設置、工事車両のルート変更など)を提示できなければ、合意形成は図れません。住民の反対運動が激化すれば、アセス手続きが停滞するだけでなく、事業そのものの撤回に追い込まれるリスクもあります。
森林開発における自然保護と生物多様性への配慮
森林における開発行為は、生態系への直接的な改変を意味します。環境アセスメントでは、特に「生物多様性」と「防災」の観点から厳しいチェックが入ります。
希少猛禽類や絶滅危惧種の生息域調査と保全措置
森林開発において最もセンシティブなのが、オオタカやクマタカなどの希少猛禽類の存在です。これらの猛禽類は生態系の頂点に位置し、その生息が確認されることは豊かな自然環境の証明となります。アセス調査で営巣地(巣)が見つかった場合、事業計画の大幅な変更(巣の周辺を保全区域として残す、工事時期を繁殖期以外にずらすなど)が不可避となります。調査自体も四季を通じて行う必要があり、最低でも1年間の現地調査期間が必要です。発見されてから対応を検討するのではなく、事前の文献調査や専門家ヒアリングでリスクを把握しておくことが重要です。
造成工事による土砂災害リスクと調整池の設計基準
森林を伐採し、ソーラーパネルを敷き詰めるために土地を造成すると、地面の保水能力が失われ、雨水が一気に下流へ流出するようになります。これが下流域での洪水や土砂災害を引き起こす原因となります。アセスメントおよび林地開発許可では、開発による雨水流出量の増加分を一時的に貯める「調整池」の設置が義務付けられます。近年は気候変動による豪雨が頻発しているため、自治体によっては国が定める基準(確率年)よりも厳しい設計基準を求めてくる場合があり、造成コストを押し上げる要因となっています。
アセス逃れとみなされないためのコンプライアンス遵守
環境アセスメントは時間とコストがかかるため、事業規模を意図的に縮小して対象から外れようとする動きが見受けられます。しかし、こうした行為は「アセス逃れ」として行政や社会から厳しく指弾され、最悪の場合は事業停止命令等のペナルティを受けることになります。
分割申請による規制回避の禁止と合算ルールの適用
よくある手口として、本来一つの大規模な発電所計画を、隣接する複数の小規模な工区に分割し、別々の法人名義で申請することで、それぞれの規模をアセス対象基準以下に抑えようとする手法があります。これは「意図的な分割」とみなされ、実質的に一体の事業であると判断された場合、全ての工区を合算した規模でアセスメントの要否が問われます。法の抜け穴を突くようなスキームは、コンプライアンス重視の現代においては通用しないばかりか、企業の社会的信用を失墜させる自殺行為です。
計画変更時に生じる再アセスメントのリスク管理
一度アセスメントを完了して着工した後でも、パネルの配置変更や出力増強などの計画変更を行う場合、その変更内容によっては再度アセスメント手続きの一部、あるいは全部をやり直す必要が生じることがあります。特に、開発区域を拡大する場合や、保全対象としていた区域に手をつけるような変更は、環境影響が著しく変化するとみなされます。将来的な拡張の可能性がある場合は、初期のアセス段階でそれを見越した調査範囲を設定しておくなど、戦略的な対応が求められます。
まとめ:再エネ開発と自然保護は対立ではなく共存の道へ
今更聞けない森林開発の環境アセスについて解説してきましたが、最も重要なのは、環境アセスメントを「クリアすべき障害」ではなく「事業のリスクを低減し、地域と共生するためのツール」として捉え直すことです。100ヘクタール未満であっても、条例や地域の自然特性によっては法アセス並みの配慮が求められます。アセス逃れのような脱法行為は論外であり、正面から環境調査を行い、得られたデータに基づいて科学的に安全性を証明することこそが、長期的に安定した再エネ事業を実現する唯一の道です。計画の初期段階から環境コンサルタント等の専門家と連携し、時間的余裕を持ったスケジュールで、自然保護と開発の境界線を慎重に見極めていきましょう。