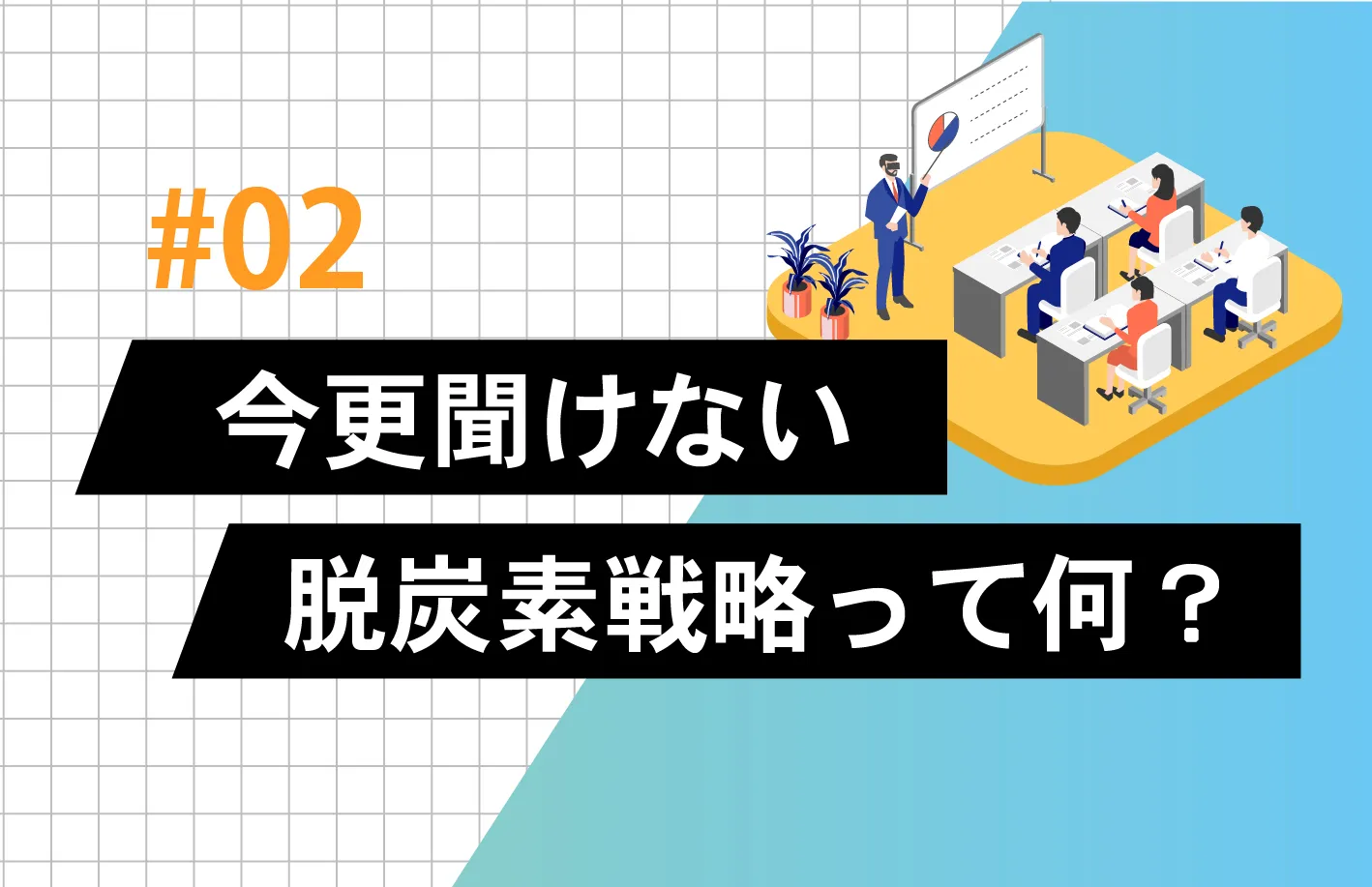「脱炭素」という言葉は聞くけれど何から手を付けていいか分からない――そんな声をしばしば耳にします。本記事は再生エネルギー業界で働く皆さんに向け、脱炭素の基本から国の支援策、現場で使える手順までを平易な言葉でまとめました。読み終えたらすぐに動けるよう、やるべきことをステップ形式で紹介します。
脱炭素とはそもそも何か
脱炭素とは「地球を暖める二酸化炭素などの排出を実質ゼロに近づける取り組み」です。植林による吸収や再エネへの切り替えで排出と吸収をつり合わせるイメージを持つと分かりやすいでしょう。世界では二〇五〇年までの達成を掲げる国が増え、日本も同じ目標を公表しています。
なぜ今注目されているのか
異常気象の多発で温暖化の影響が身近になり、企業に対しても「環境に配慮した製品を選びたい」という要望が高まっています。その結果、脱炭素に遅れると取引や資金調達が難しくなるケースが出てきました。
カーボンニュートラルとの違い
脱炭素もカーボンニュートラルも目指すゴールは同じですが、脱炭素はより幅広い行動を指す言葉として使われることが多くなっています。再エネの導入だけでなく、節電やリサイクルまで含めた総合的な取り組みを表現する際に便利です。
脱炭素がビジネスにもたらすチャンス
義務として取り組むだけでなく「ビジネスチャンスになる」と考える企業が増えています。環境にやさしい商品やサービスは付加価値が高く、価格競争に巻き込まれにくいメリットがあります。
新しい市場の創出
例えば太陽光の屋根貸しサービスや電気自動車向け充電設備など、これまでなかった市場が次々に生まれています。早めに取り組むことで先行者利益を得やすくなります。
資金調達がしやすくなる
銀行や投資家は環境配慮型のプロジェクトに資金を回す傾向があります。「グリーンボンド」や「サステナビリティ連動融資」といった仕組みを活用すれば、従来よりも有利な条件で借り入れできる場合があります。
日本と世界の動きを知ろう
世界の潮流を知れば、国内で何が起こるかを予測しやすくなります。海外取引がある会社は特に注目です。
世界的な規制強化
欧州では二〇二五年から、高い排出量の製品に追加課税を行う制度が始まります。日本の部品が欧州に輸出される場合も対象になるため、今から準備が必要です。
国内の支援策
経済産業省は再エネ導入や省エネ設備更新に使える補助金を毎年公募しています。要件は年ごとに変わるため、最新情報をチェックしましょう。
脱炭素を進める5つのステップ
壮大に見える目標も、順序立てれば着実に進みます。ここでは五つの基本ステップを紹介します。
1 現状を測る
最初にやるべきは「自社がどれだけ排出しているか」を把握することです。電力会社の請求書や燃料の使用量から計算できるツールが公開されています。
2 目標を決める
二〇三〇年までに二〇%削減など、ゴールを数字で示すと社内の理解が進みます。期限と担当部署を明確にすると実行力が高まります。
3 行動を洗い出す
再エネ導入・設備更新・省エネ教育など、できることをリスト化しましょう。費用と効果を見比べ、優先順位をつけると実行しやすくなります。
4 資金をつける
補助金や低利融資を組み合わせると初期費用を抑えられます。金融機関に相談する際は、排出削減の効果を数字で示すと説得力が増します。
5 効果を確認する
行動後は必ず排出量を再計測し、計画と比べます。ズレがあれば原因を探して早めに修正しましょう。
再エネ発電ごとのポイント
発電方式によって準備や運用のコツが変わります。ここでは代表的な三つに絞って見ていきます。
太陽光
屋根や遊休地を使えるため、比較的着手しやすい方法です。発電量は天候に左右されるので、設備の向きと角度が重要になります。
風力
海や山間部など風が強い場所に適しています。設置には環境アセスメントが必要な場合があるため、計画段階で時間を見込んでおきましょう。
バイオマス
木くずや食品残さなどを燃料にできます。燃料調達が安定するかが成否を分けるポイントです。
お金の集め方とコストの下げ方
設備投資は資金面が最大のハードルといわれますが、工夫次第で負担を減らせます。
補助金を活用する
国や自治体が公募する補助金は導入コストの三〜五割をカバーするものもあります。締切が近いものは早めに申請書を作りましょう。
PPAモデル
電力会社や投資家が設備を設置し、企業は電気料金として支払う形です。初期費用ゼロで再エネを導入できるため、近年急速に広がっています。
サプライチェーン全体で考える
自社の発電量を再エネに置き換えるだけでなく、仕入れ先や輸送も含めた排出を減らすと評価が上がります。
仕入れ先との協力
「再エネを使った製品を優先購入する」という方針を示すと、取引先も脱炭素に動きやすくなります。
輸送の効率化
配送ルートを見直すだけでも排出量は減ります。大型車と小型車を使い分けることで燃料消費を抑えた事例もあります。
成功している会社の事例
最後に、分かりやすい成功例を二つ紹介します。
地域工務店の太陽光導入
従業員三十人の工務店が倉庫屋根に太陽光を設置し、電気代を年百万円削減しました。発電量の見える化画面を来店客に見せることで受注にもつながっています。
食品メーカーの省エネ診断
冷凍設備のインバーター化と照明のLED化で、年間排出量を一割減らしました。補助金を活用し実質負担は五年で回収済みです。
これからの流れ
脱炭素は一時的なブームではなく、今後ずっと続く社会の大きな流れです。早く動いた企業ほど取引拡大や資金調達で有利になり、社員のモチベーション向上にもつながります。本記事を参考に、まずは現状把握と目標設定から始めてみましょう。
まとめ
脱炭素は難しそうに見えますが、五つのステップで分解すれば確実に進められます。再生エネルギー業界で働く皆さんは、今回紹介した方法を活用しながら行動を一歩ずつ積み重ねてください。早めの着手がビジネスチャンスを広げ、持続可能な社会づくりに貢献します。