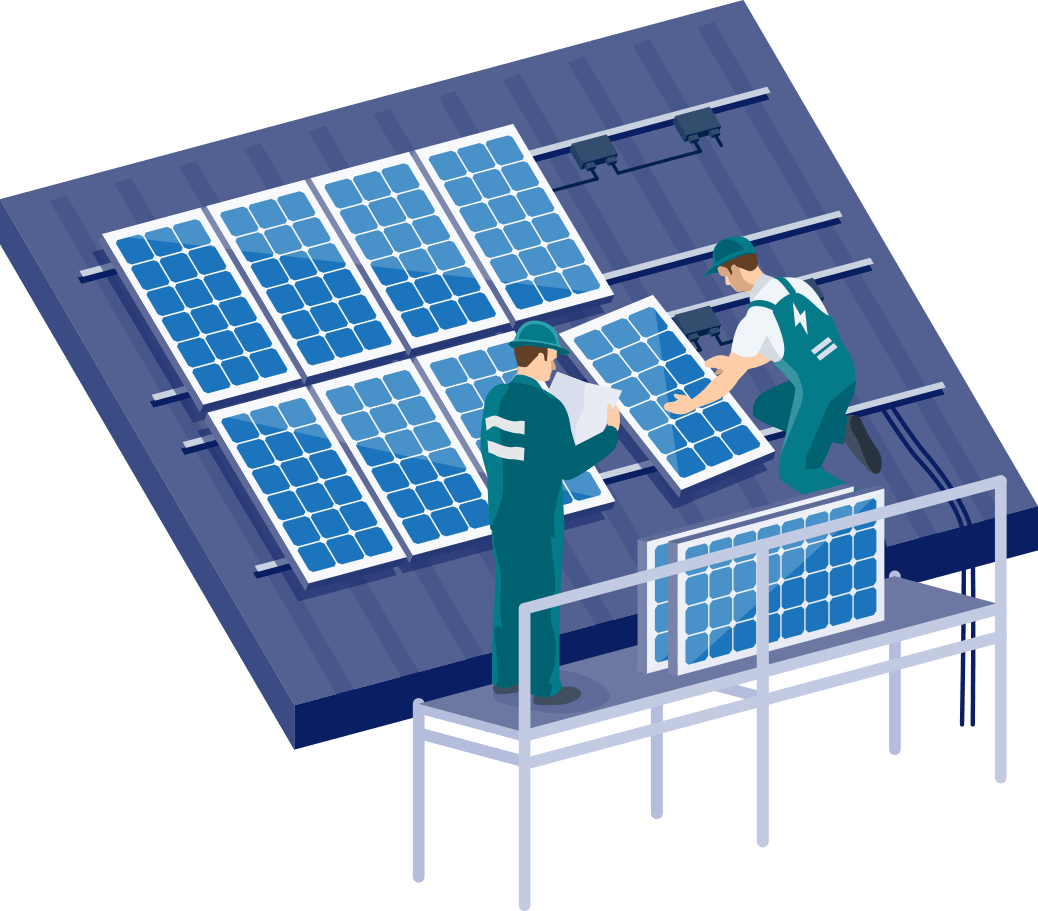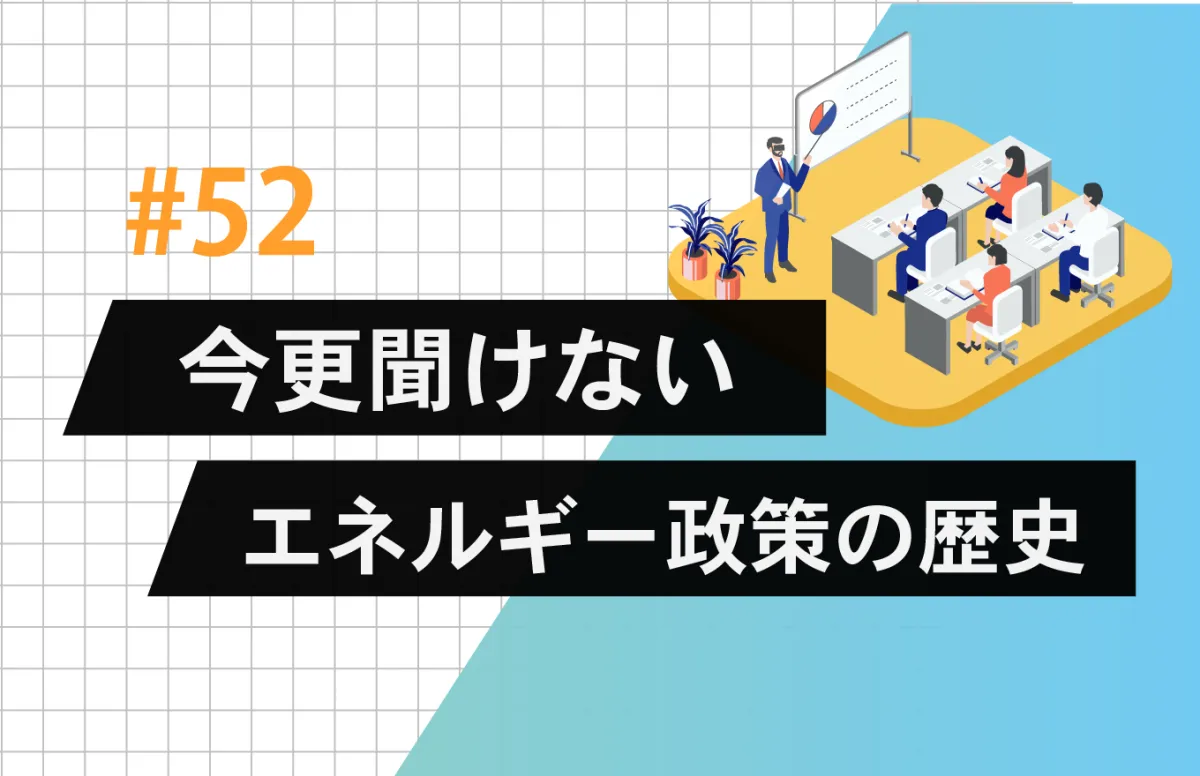今更聞けないエネルギー政策の歴史
日本はどうやって再エネ社会を目指してきたか
再生可能エネルギーの導入に携わる皆様にとって、現在の政策や市場環境は日々の業務に直結しています。しかし、現在の状況がどのような歴史的背景から生まれたのか、その道のりを深く理解できているでしょうか。
本記事では、「今更聞けないエネルギー政策の歴史」をテーマに、日本のエネルギー政策が歩んできた変遷を、オイルショックによる安定供給重視の時代から、地球温暖化対策、そして東日本大震災を経て再生可能エネルギー社会を目指すに至るまでの道のりを詳細に解説します。
過去の政策決定の意図と、それが現在の再エネ市場にどう影響しているのかを理解することで、皆様の事業戦略に役立つ示唆が得られるでしょう。
エネルギー政策の歴史を紐解く オイルショックがもたらした教訓
日本のエネルギー政策の根幹は、二度のオイルショックによって形成されたと言っても過言ではありません。第二次世界大戦後、急速な経済成長を遂げた日本は、安価な石油に大きく依存する構造(石油比率の高い電源構成)を確立しました。
しかし、1970年代に発生した中東戦争に端を発するオイルショックは、この構造の脆さを露呈させ、国家のエネルギー安全保障に対する意識を決定的に変えました。この経験から、日本のエネルギー政策は、「安定供給の確保」を最重要課題として位置づけることになったのです。
石油依存からの脱却と原子力・石炭へのシフト
オイルショック後、日本政府は「石油代替エネルギー開発計画」を推進し、エネルギー源の多角化を強力に推し進めました。この政策の柱となったのが、原子力発電と石炭火力発電の導入拡大です。
原子力は、準国産エネルギーとして高い安定供給能力を持つとされ、国策として推進されました。また、石炭は世界中に広く分布し、価格変動リスクが石油ほど高くないことから、重要なベースロード電源として位置づけられました。
この時期の政策の焦点は、環境負荷よりも、とにかく「供給の安定性」と「経済性」の確保にあったと言えます。水力発電を除き、この時点ではまだ大規模な再生可能エネルギーへの本格的な着目はされていませんでした。
地球温暖化問題の顕在化と再生可能エネルギーへの意識の変化
1990年代に入り、地球温暖化問題が国際的な課題として顕在化すると、日本のエネルギー政策にも大きな転機が訪れます。1997年の京都議定書採択は、CO₂排出量削減という新たな第三の柱を、これまでの「安定供給」と「経済性」に加えることを意味しました。
この頃から、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーが、温暖化対策の有効な手段として注目され始めます。政策としては、「新エネルギー法」の制定や、RPS(固定価格買取制度の前身)制度の試行的な導入など、再生可能エネルギーの普及を促進するための土壌が徐々に整備されていったのです。ただし、この段階では、再エネはまだ主力電源というよりも、補助的な役割として捉えられていました。
再生エネルギー普及の夜明け FIT制度導入とその功罪
2010年代に入ると、日本のエネルギー政策は、再生可能エネルギーの導入において最も劇的な変化を遂げます。その中心にあったのが、再生可能エネルギーの固定価格買取制度、通称FIT制度の導入です。この制度は、再エネ事業を本格的な産業として確立させるための起爆剤となりました。
東日本大震災とエネルギー政策の大転換
2011年3月の東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故は、日本のエネルギー政策の歴史における最大級の転換点となりました。それまで「準国産エネルギー」として推進されてきた原子力発電の安全性に対する懸念が一気に高まり、国内のほぼすべての原子力発電所が停止するという事態に至りました。
この結果、エネルギーの「安全性」が、これまでの三原則(安定供給、経済性、環境適合)に加えられることになり、電源構成の見直しが喫緊の課題となりました。この未曾有の危機的状況が、再生可能エネルギーを単なる温暖化対策ではなく、日本のエネルギー安全保障の鍵として本格的に位置づける大きなきっかけとなったのです。
固定価格買取制度(FIT)による再エネの爆発的導入
震災後の2012年7月、FIT制度(Feed-in Tariff)が導入されました。この制度は、再生可能エネルギーで発電された電力を、国が定めた固定価格で一定期間、電力会社が買い取ることを義務付けるものです。特に太陽光発電に対して、世界的に見ても非常に高い買取価格が設定された結果、国内外から大規模な投資が呼び込まれ、太陽光発電設備が爆発的に増加しました。
この制度は、再エネの黎明期における初期投資リスクを大幅に低減し、技術開発とコストダウンを促進する上で計り知れない貢献をしました。再生エネルギー業界の多くの方々が、この制度の恩恵を受けて事業をスタートしたと言えるでしょう。
FIT制度の抱える課題と制度改正の道のり
一方で、FIT制度はいくつかの大きな課題も生み出しました。特に、高すぎる買取価格が国民負担(賦課金)として積み上がり、電力コストの増加を招いた点です。また、発電量が天候に左右される太陽光発電が急増したことで、電力系統の安定化に対する懸念も増大しました。
さらに、買取価格が固定されるため、事業者が市場の需給状況を意識せず発電を行う「市場との乖離」も問題となりました。これらの課題に対応するため、政府はFIT制度を段階的に見直し、価格競争を促す入札制度の導入や、地域との共生を促すための認定要件の厳格化などを進めていきました。この一連の制度改正は、再エネを「保護育成」の段階から「自立」の段階へ移行させるための不可避なプロセスでした。
再エネ自立への挑戦 FITからFIPへの移行
FIT制度の役割が一定程度完了し、再生可能エネルギーがコスト競争力を持ち始めたことを背景に、日本のエネルギー政策は次のステップである「再エネの主力電源化」に向けて舵を切りました。その中核となるのが、2022年4月に導入されたFIP制度です。
FIP制度導入の目的と基本的な仕組み
FIP(Feed-in Premium)制度は、再生可能エネルギー発電事業者が市場価格で電力を販売し、それに加えて一定の「プレミアム(奨励金)」を上乗せして受け取る仕組みです。この制度の最大の目的は、再生可能エネルギー発電事業者を電力市場に組み込むことです。
市場価格が低いときにはプレミアムが大きくなり、市場価格が高いときにはプレミアムが小さくなるように設計されており、事業者は市場の需給に応じて発電や販売のタイミングを工夫するインセンティブが働きます。
これにより、再エネが自律的に市場原理の中で競争し、電力系統の安定化に貢献することが期待されます。FIT制度がもたらした「市場との乖離」を是正し、再エネを真の主力電源とするための重要な一歩と言えるでしょう。
アグリゲーターの役割と再エネ業界に求められる変革
FIP制度の導入により、再生可能エネルギー業界には新たなプレイヤーであるアグリゲーター(束ね役)の役割が非常に重要になってきています。アグリゲーターは、多数のFIP認定電源の発電量を予測・管理し、市場での最適な売買を行うことで、事業者の収益最大化を支援します。
これまでのFIT制度下では、発電すれば固定価格で買い取られるため、発電予測の精度や市場取引に関する知識は必ずしも重要ではありませんでした。しかし、FIP制度下では、これらの市場連動型のノウハウが事業の成功を左右します。
再生エネルギー事業者自身も、VPP(バーチャル・パワー・プラント)技術の導入や蓄電池の併設など、発電量を制御する能力を高める変革が強く求められています。
長期的なエネルギー基本計画が示す2050年目標
日本のエネルギー政策は、数年ごとの「エネルギー基本計画」によってその方向性が定められています。最新の計画では、2050年カーボンニュートラルという野心的な目標が掲げられ、再生可能エネルギーが「主力電源」として明確に位置づけられました。
2030年の電源構成目標では、再エネ比率を大幅に引き上げる計画が示されており、これは、これまでの政策の積み重ねと、今後のFIP制度による市場競争促進によって達成を目指すものです。水素、アンモニア、洋上風力発電といった次世代エネルギー技術への投資が加速しており、エネルギー政策の歴史は、今まさに「再エネ社会の完成」という最終章へと向かっているところです。
まとめ 今後のエネルギー政策の歴史を創る再生エネルギー業界の役割
エネルギー政策の歴史を振り返ると、オイルショックによる「安定供給」の重視から始まり、環境対策としての「再エネ導入」、そして震災後の「安全性」重視を経て、現在の「再エネ主力電源化」へと至る、一貫した進化の道筋が見えてきます。
FIT制度による普及拡大という「助走期間」を終え、日本は今、FIP制度を通じて再生可能エネルギーを真の主力電源とするための「競争と自立」の段階に移行しています。再生エネルギー業界の皆様は、過去の政策の背景を理解することで、なぜFIP制度が導入されたのか、なぜ市場対応力が求められているのか、その本質を把握できるはずです。
これからの日本のエネルギー政策の歴史を創るのは、市場の変動に対応し、技術革新を恐れず、新たな価値提供に挑戦する皆様です。この変革期をチャンスと捉え、再エネ社会の実現に向けて、より一層の貢献を果たしていきましょう。
| 施工完了日 | - |
|---|---|
| 地域 | - |
| 施工内容 | - |
| 業種 | - |
| システム容量 | - |
| 仕様 | - |