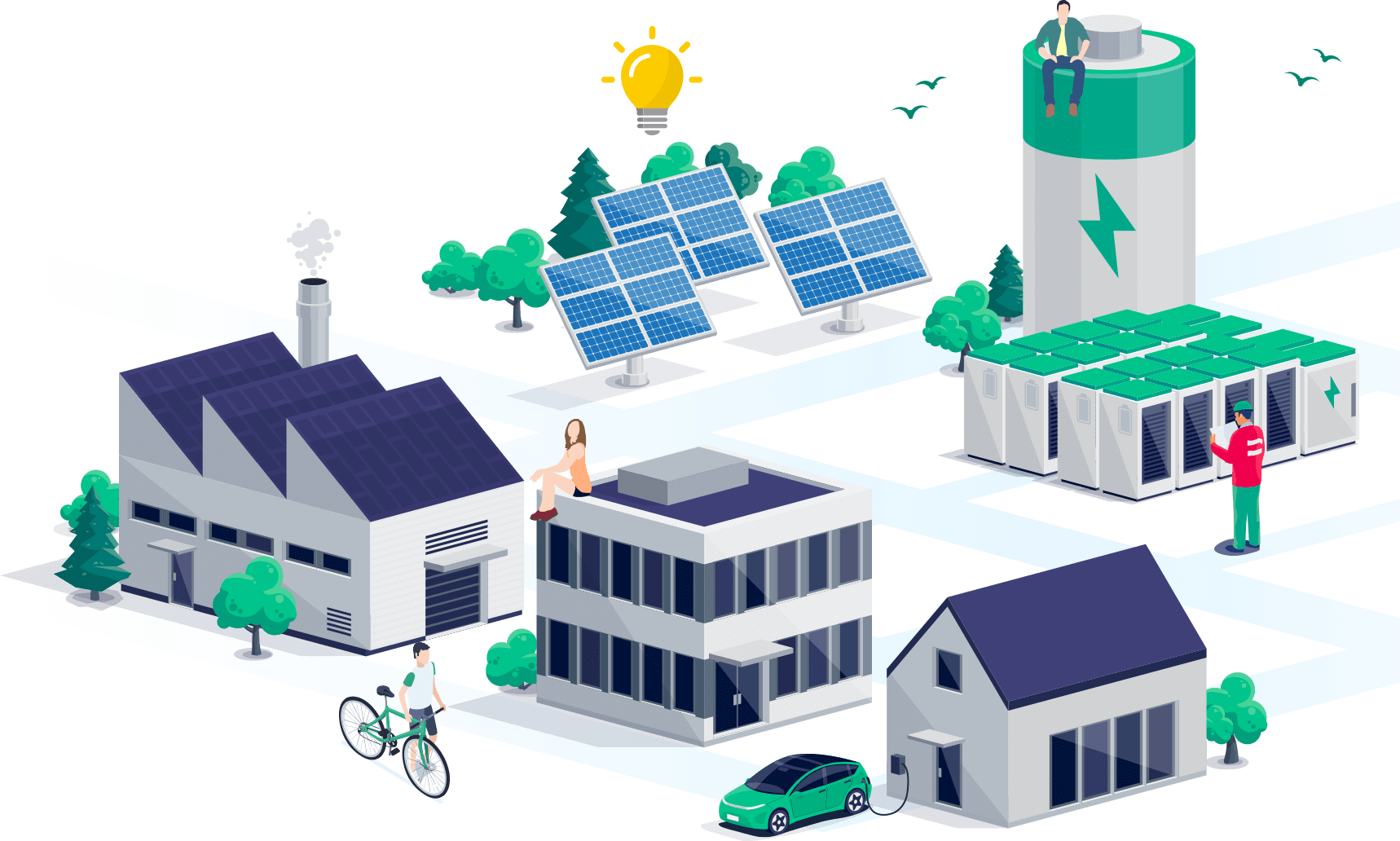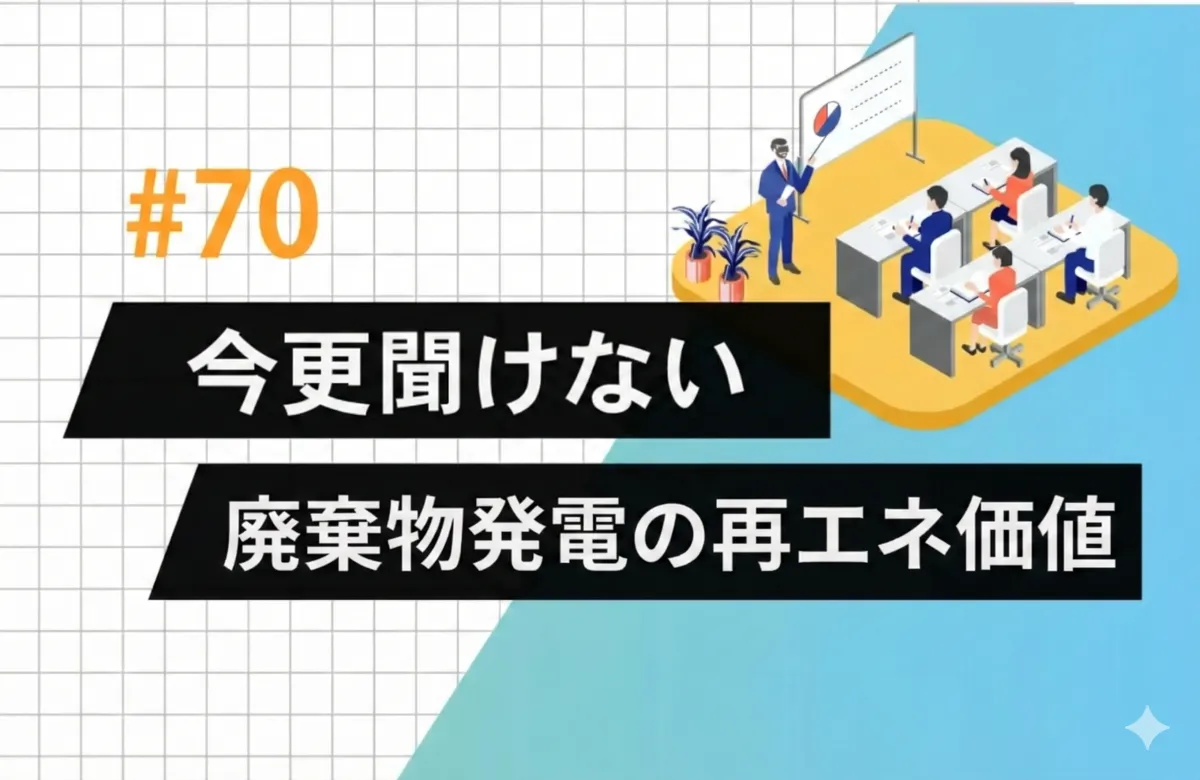今更聞けない廃棄物発電の再エネ価値
ゴミ燃焼電力はグリーン認定されるか
再生可能エネルギーの導入拡大が叫ばれる中、都市部を中心に安定した電力を供給し続けている「廃棄物発電(ごみ発電)」の存在感が増しています。しかし、再エネ業界の関係者であっても、「ゴミを燃やした電気はすべて再エネ扱いになるのか?」「FIT制度やRE100においてどのような位置づけなのか?」という点については、曖昧な理解に留まっているケースが少なくありません。本記事では、今更聞けない廃棄物発電の再エネ価値について、バイオマスと化石燃料由来の線引き、環境価値取引の実務、そして脱炭素社会における将来性までを徹底解説します。
廃棄物発電は「再生可能エネルギー」に含まれるのか
結論から言えば、廃棄物発電はそのすべてが再生可能エネルギーとして認められるわけではありません。ゴミという混合物の中に含まれる「ある成分」由来のエネルギーだけが、グリーンな電力としてカウントされる仕組みになっています。まずは、この基本的な定義と構造を正しく理解することから始めましょう。
バイオマス分とプラスチック分の明確な境界線
廃棄物発電で燃やされるゴミ(一般廃棄物や産業廃棄物)は、大きく2つの性質に分けられます。一つは、紙くず、木くず、生ゴミ(食品廃棄物)といった生物由来の有機物である「バイオマス分」。もう一つは、廃プラスチックや合成繊維など、石油を原料とする「化石燃料由来分」です。
日本の法令(エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律など)や国際的な基準において、再生可能エネルギーとして認められるのは、前者の「バイオマス分」を燃焼させて得られた電力のみです。後者の廃プラスチックを燃やした電力は、あくまで化石燃料を燃やしたのと同義とみなされ、再エネ価値は認められません。つまり、一つの焼却炉から生まれた電力であっても、その中身は「グリーン電力」と「グレー電力(化石電源)」が混在しているのです。
エネルギー供給構造高度化法における位置づけ
法的な定義をさらに掘り下げると、廃棄物発電は「非化石エネルギー源」の一つとして位置づけられています。しかし、ここでも「再生可能エネルギー源(バイオマス)」と「それ以外の非化石エネルギー源(廃プラスチック等の燃焼熱利用)」という区分が存在します。実務上は、焼却炉に投入されるゴミの組成分析を行い、その熱量比率に基づいて、発電電力量のうち何割が再エネ(バイオマス)で、何割が非再エネ(化石由来)かを厳密に計算する必要があります。この「仕分け」が、廃棄物発電の環境価値を決定づける最重要プロセスとなります。
FIT制度(固定価格買取制度)における廃棄物発電の扱い
再生エネルギービジネスにおいて、FIT制度は切っても切り離せない存在です。太陽光や風力と同様に、廃棄物発電もFITの認定対象となっていますが、その適用条件や買取価格の設定には独自のルールがあります。
一般廃棄物と産業廃棄物による認定区分の違い
FIT制度では、廃棄物発電は「バイオマス発電」のカテゴリーに含まれます。しかし、燃料となるゴミの種類によって扱いが異なります。
1. **一般廃棄物(家庭ごみ等)**:市町村が運営する清掃工場などが該当します。一般廃棄物は紙や生ゴミの比率が高いため、比較的再エネ価値が高いとみなされますが、FITの買取対象となるのは、あくまで「バイオマス比率」に相当する電力分だけ、あるいは管理の煩雑さを避けるために予め設定された一定の比率(例:全発電量の◯%など)とみなして買い取るケースなど、制度上の変遷があります。
2. **産業廃棄物**:工場や事業所から出るゴミです。こちらは廃プラスチックの比率が高い場合が多く、バイオマス発電としての認定を受けるには、木くずや紙くずなどのバイオマス資源を専焼、あるいは高い比率で混焼していることを証明する必要があります。
バイオマス比率に応じた買取価格の決定ロジック
FIT認定を受ける際、最も重要なのが「バイオマス比率」の証明です。例えば、発電した電力が1,000kWhあり、投入したゴミの熱量ベースでのバイオマス比率が60%だった場合、600kWh分がFIT価格(例:17円/kWhなど)で買い取られ、残りの400kWh分は通常の電力市場価格(回避可能原価等)での取引となります。したがって、廃棄物発電事業者が収益を最大化するためには、できるだけ廃プラスチック(化石由来)を減らし、バイオマス(生物由来)の比率を高めるような燃料調達や分別収集が求められることになります。
環境価値取引における「非化石証書」の分類と活用
電気が持つ「環境価値」を切り離して取引する「非化石証書」市場においても、廃棄物発電由来の証書は特殊な立ち位置にあります。RE100やSBT(Science Based Targets)を目指す企業が証書を購入する際、この違いを理解していないと目標達成にカウントされないリスクがあります。
「再エネ指定あり」と「再エネ指定なし」の違い
非化石証書には、大きく分けて「再エネ指定あり」と「再エネ指定なし」の2種類が存在します。
* **再エネ指定あり(FIT非化石証書など)**:太陽光、風力、そして廃棄物発電のうち「バイオマス分」に相当する証書です。これはRE100等の再エネ目標に活用できます。
* **再エネ指定なし**:廃棄物発電のうち「廃プラスチック分」の燃焼エネルギーに由来する証書です。これは「非化石電源(化石燃料を直接燃やしたわけではない)」とは認められますが、「再生可能エネルギー」ではありません。したがって、高度化法における小売電気事業者の非化石電源比率向上には寄与しますが、RE100企業が求める「再エネ100%」の達成には使えないのです。
コーポレートPPAや小売電気事業者による調達戦略
近年、企業が発電所から直接再エネを購入するコーポレートPPAが増えていますが、廃棄物発電所と契約する場合も同様の注意が必要です。契約電力の全量が再エネとして認められるわけではなく、あくまでバイオマス比率分のみがグリーン電力となります。小売電気事業者が「実質再エネ100%プラン」を組成する場合、廃棄物発電からの調達分については、不足する再エネ価値を他の再エネ証書で補填するなどの調整が必要になるケースがあります。実務担当者は、トラッキング付き非化石証書の属性情報を詳細に確認するリテラシーが必須です。
廃棄物発電特有のメリットと抱えるジレンマ
再エネとしての価値は「部分的」である廃棄物発電ですが、太陽光や風力にはない独自の強みを持っています。一方で、世界的な脱炭素・脱プラスチックの潮流の中で、難しい立場に立たされているのも事実です。
天候に左右されない安定したベースロード電源としての機能
太陽光は雨が降れば発電せず、風力は風が止まれば止まります。これに対し、廃棄物発電はゴミがある限り24時間365日、一定の出力で発電し続けることができます。都市部において、地産地消型の安定電源(ベースロード電源)として機能し、地域マイクログリッドの核となり得るポテンシャルを持っています。また、災害時には自立運転機能を持つ清掃工場が、地域の避難所へ電力を供給する防災拠点としての役割も期待されています。この「安定性」と「公共性」は、他の変動型再エネにはない大きな価値です。
サーマルリサイクルへの国際的な批判と脱炭素の壁
一方で、欧州を中心に「ゴミを燃やして熱回収すること(サーマルリサイクル)」自体への風当たりが強まっています。EUのタクソノミー(持続可能な経済活動の分類)では、廃棄物焼却は資源循環(マテリアルリサイクル)を阻害し、CO2を排出する行為として、グリーン投資の対象から外される傾向にあります。日本は「熱回収も有効な資源利用」という立場をとっていますが、廃プラスチックを燃やすことで化石燃料由来のCO2が発生することは避けられません。今後、炭素税や排出量取引が本格化すれば、廃棄物発電所が排出するCO2コストが経営を圧迫する可能性があります。
実務担当者が押さえるべきバイオマス比率の算定方法
実際に廃棄物発電の再エネ価値を算定する現場では、どのような手法が用いられているのでしょうか。正確な計測は難しいため、いくつかの推定方法が認められています。
組成分析法と管理図法による比率の推定
ゴミピットに搬入されるゴミをサンプリングし、手作業で「紙・布・木(バイオマス)」と「プラスチック(非バイオマス)」に分別して重量比や熱量比を求める「組成分析法」が基本です。しかし、日々変動するゴミの質を毎日分析するのは現実的ではありません。そのため、過去のデータや統計に基づいた係数を用いたり、ボイラーの発生熱量とCO2排出量から逆算したりする簡易的な手法も採用されています。FIT認定や証書発行の審査では、この算定根拠の合理性が厳しく問われるため、定期的な組成調査とデータの蓄積が欠かせません。
プラスチック資源循環促進法による分別強化の影響
2022年に施行されたプラスチック資源循環促進法により、家庭や企業からの廃プラスチックの分別回収・リサイクルが強化されています。これにより、焼却炉に持ち込まれるゴミの中からプラスチック分が減少し、結果として相対的にバイオマス比率が向上するという現象が起きています。これは再エネ価値を高める上では追い風ですが、一方でプラスチックという高カロリーな燃料が減ることで、焼却炉の燃焼温度管理が難しくなったり、発電出力が低下したりする技術的な課題も生じています。燃料の質的変化に対応した運転管理が、今後の実務のポイントとなります。
次世代の廃棄物発電とCCUS(CO2回収・貯留)の可能性
廃棄物発電が真に「脱炭素電源」として生き残るためには、CO2排出という最大の弱点を克服する必要があります。そこで注目されているのが、CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)技術との融合です。
排ガスからのCO2回収で「カーボンネガティブ」を目指す
廃棄物発電所の煙突から出る排ガスからCO2を分離・回収する実証実験が各地で進んでいます。特に、バイオマス分から発生したCO2(もともと大気中から植物が吸収したもの)を回収して地中に貯留すれば、大気中のCO2を実質的に減らす「BECCS(Bio-energy with Carbon Capture and Storage)」となり、カーボンネガティブ(マイナス排出)を実現できます。これにより、廃プラスチック由来のCO2排出を相殺し、発電所全体としてゼロエミッション、あるいはマイナスエミッションを達成する未来図が描かれています。
メタン化(バイオガス発電)とのハイブリッド運用
生ゴミなどの水分が多いバイオマスごみは、直接燃やすよりも、メタン発酵させてバイオガスを取り出し、ガスエンジンで発電する方が効率的です。最近では、焼却施設にメタン発酵施設を併設し、発酵残渣を焼却炉で処理するハイブリッド型の施設も増えています。これにより、純度の高いバイオマスエネルギー(バイオガス)と、廃棄物発電の熱利用を組み合わせ、地域全体のエネルギー効率を最大化する取り組みが進んでいます。
まとめ:廃棄物発電の価値は「分別」と「技術」で進化する
今更聞けない廃棄物発電の再エネ価値について解説してきましたが、結論として、ゴミ発電は「条件付きの再エネ」であり、その価値は投入されるゴミの質と、そこから環境価値を抽出する計算ロジックによって決まります。業界関係者の皆様には、単に「ゴミを燃やせばエコ」という認識を改め、バイオマス比率の向上、非化石証書の適切な管理、そしてCCUSなどの新技術導入に向けたロードマップを描くことが求められます。
廃棄物発電は、都市インフラの要でありながら、脱炭素の最前線に立つポテンシャルを秘めています。まずは自社が関わる施設や契約している電力プランにおいて、バイオマス比率がどのように算定され、どのような環境価値が付与されているのか、詳細なデータを確認することから始めてみてください。その一歩が、より確実でグリーンなエネルギー戦略の構築につながります。